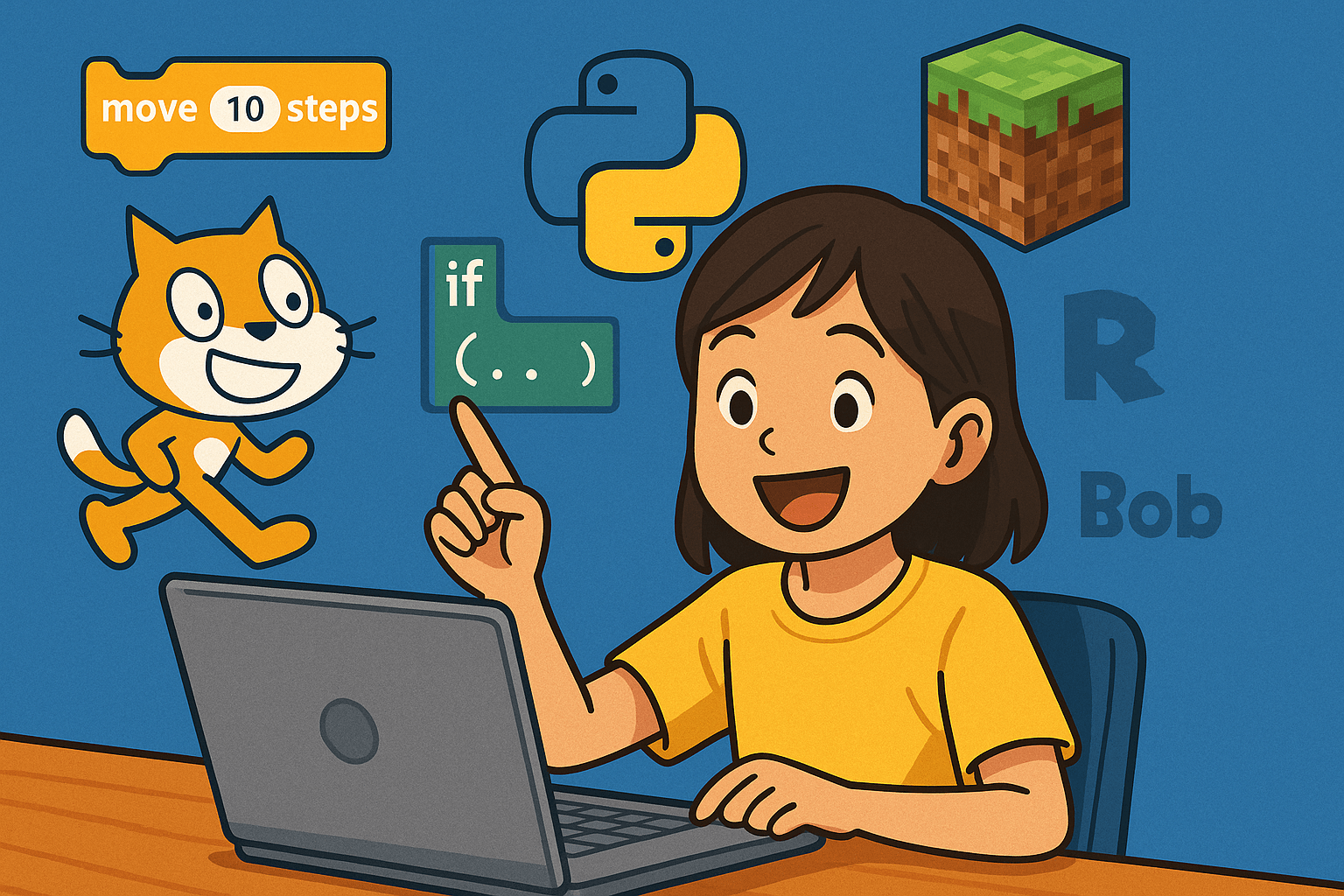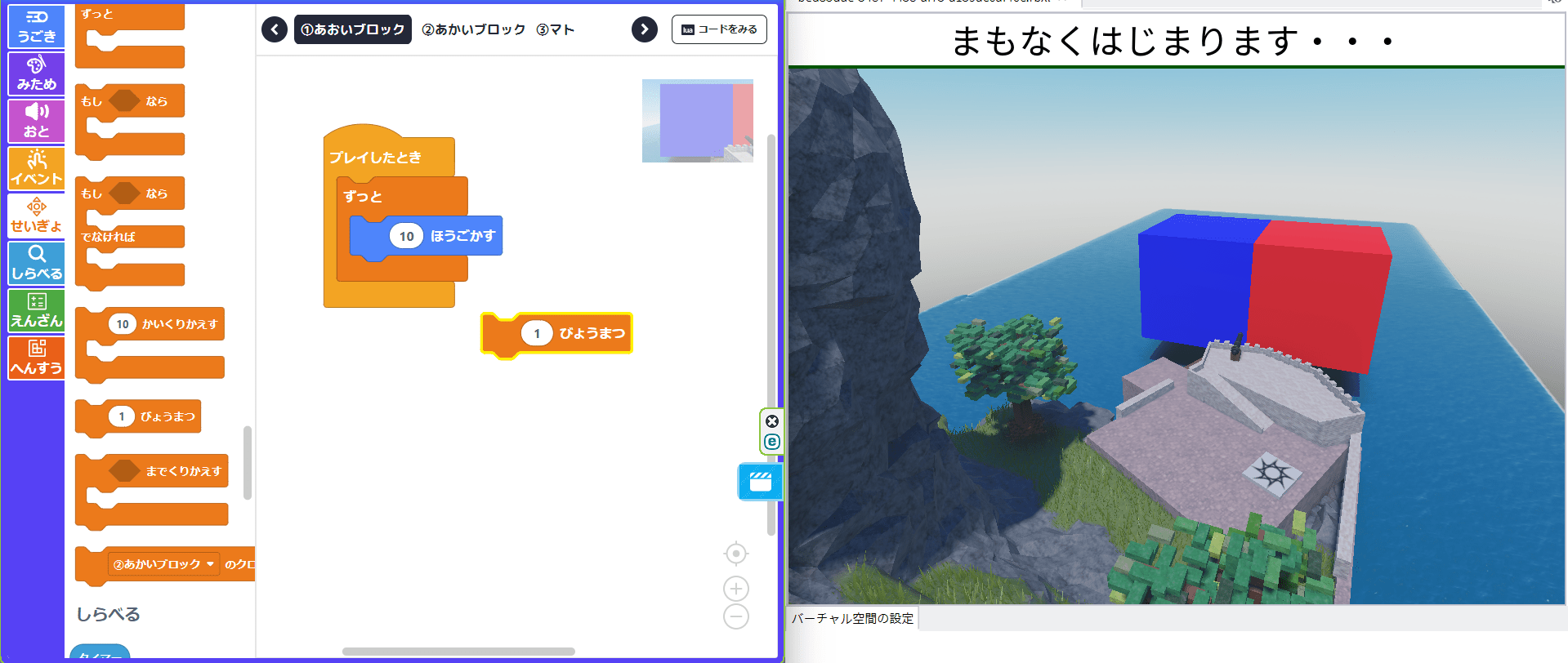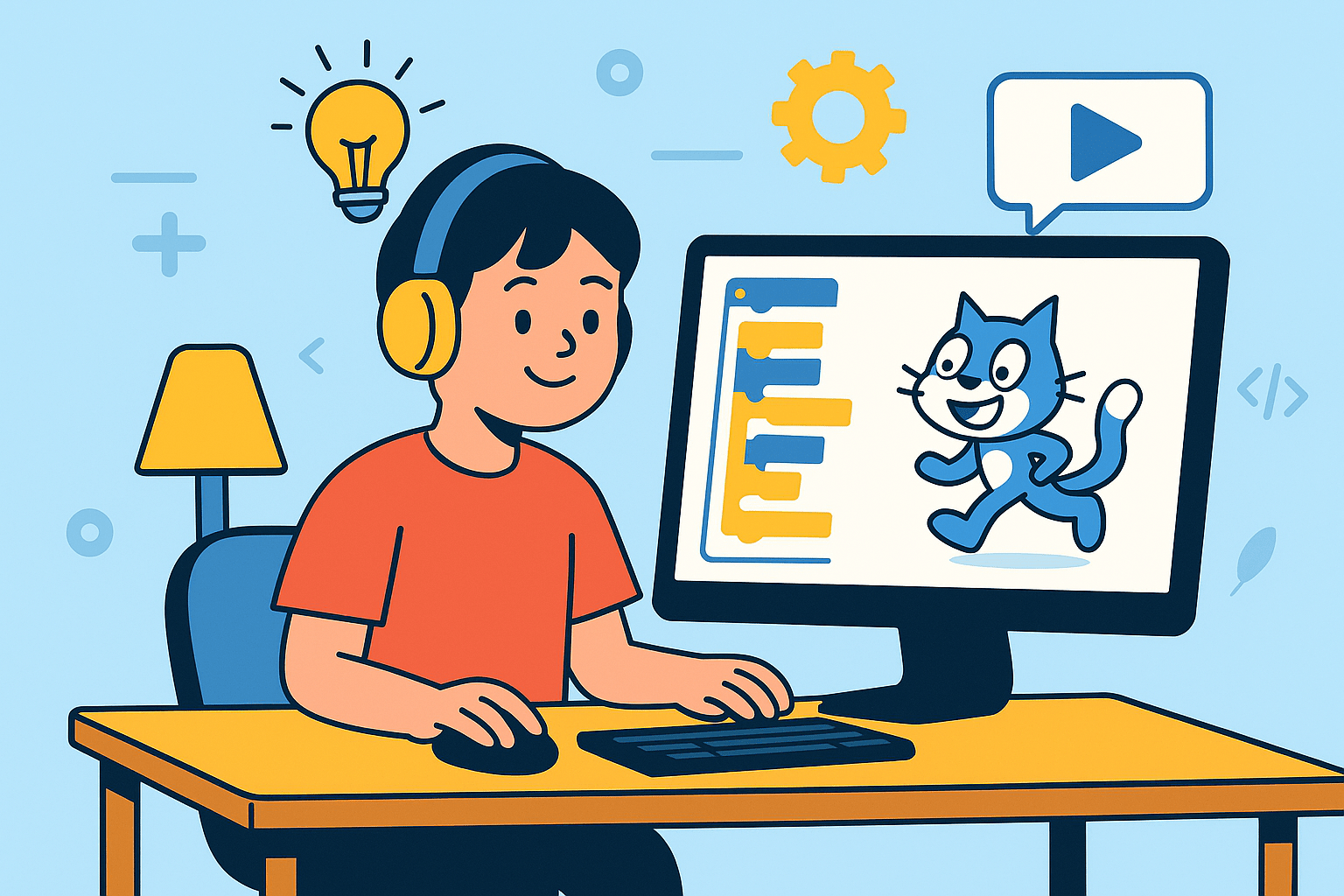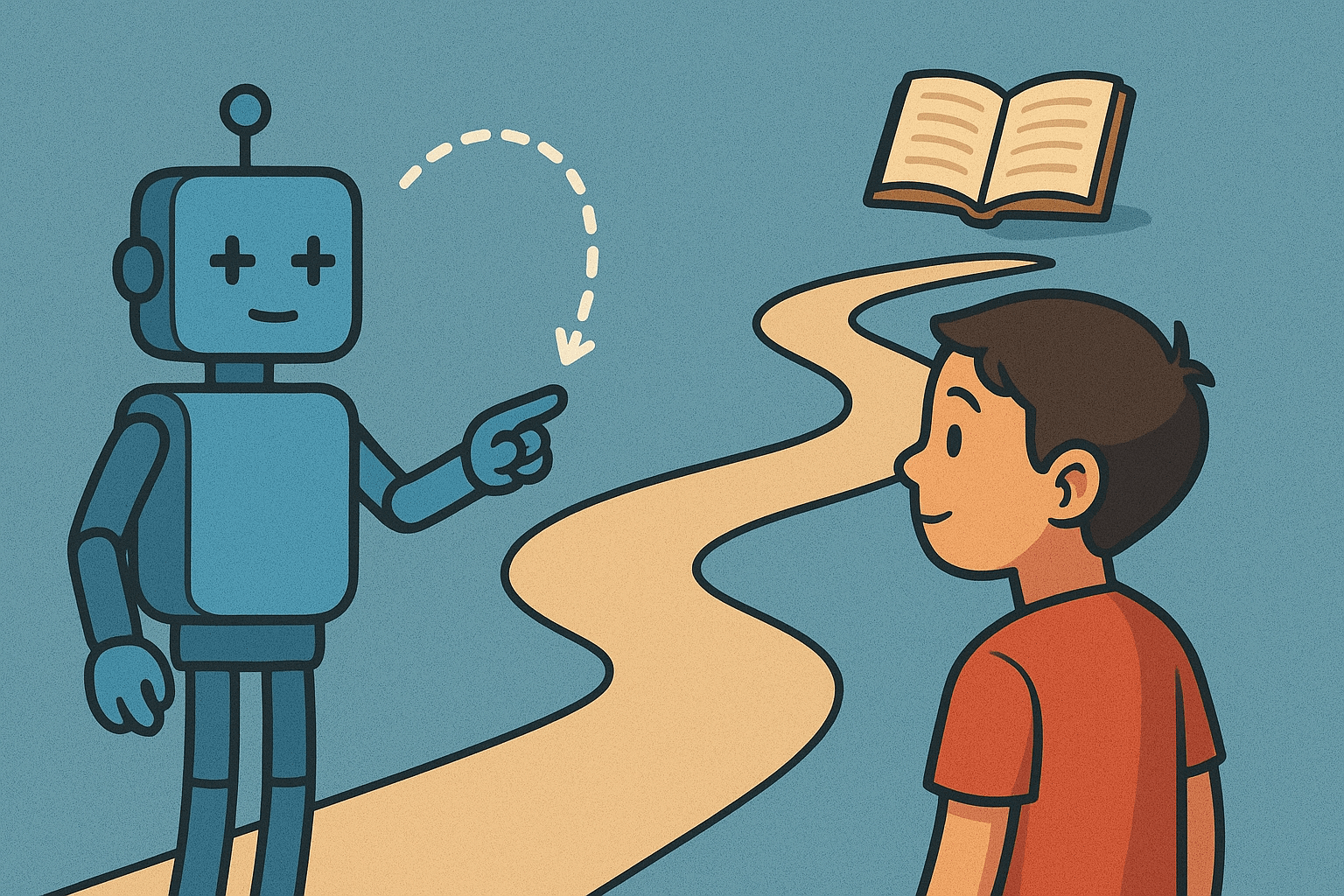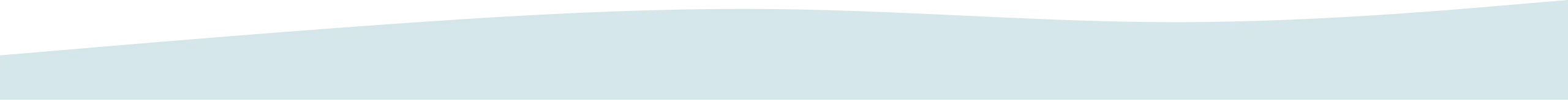学校や他の習いごととちがう「プログラミング教室」
「コードがこわれた!…でもなおせるかも。」
これは、ある小学生がスクラッチで作ったゲームが3回目に止まったときに言った言葉です。おこっているわけじゃありません。むしろ、集中して、わくわくして、自信を持っていました。
ふつうの授業では、なかなか聞かないセリフです。
日本の小学生は、毎日きまったルールの中で行動しています。「これを言いなさい」「ここに書きなさい」「これはおぼえなさい」。放課後もおなじです。ピアノ、水泳、英語、塾……どれも大人の指示にそって、正しいやり方をくりかえします。
でもこどもプログラミング教室はちがいます。
「自分で考える力」が育つ
プログラミングでは、だれかのまねをするのではなく、自分の頭で考えます。わざとこわしてみたり、ちがうやり方をためしたり、自分でトラブルを見つけて直したりします。だれも「これが正解」とは言いません。
だからこそ、考える力がのびます。
小学生には「スクラッチ(Scratch)」が人気
低学年の子どもたちにはスクラッチ(Scratch)を使います。見た目はゲームのようですが、本物のプログラミングです。カラフルなブロックをつなげて、キャラクターの動きを作ります。
ある2年生の子は、ネコがネズミをおいかけるゲームを作りました。でも、ネズミがすぐに消えてしまいます。「スピードが速すぎる?」「コードをまちがった場所に入れた?」など、いろいろ考えて、30分かけて直しました。
その30分間、だれに言われたわけでもなく、自分でがんばっていたのです。
上の学年では「パイソン(Python)」や「マインクラフト」「ロブロックス」
高学年になると、パイソン(Python)に進みます。文字を打ってコードを書く本格的なスタイルです。もちろんむずかしいですが、考え方はスクラッチとおなじです。
ある子が if 文の最後に「:」をわすれて、「パイソン、また意地悪してきたー!」と言っていました。教室中が笑いました。でもすぐに自分で気づいて、なおしていました。
ほかにもマインクラフト(Minecraft)やロブロックス(Roblox)を使ったプログラミングもあります。すでに知っているゲームの中で、自分の世界を作ったり、ルールを作ったりします。つまり、ただ「プレイ」するだけじゃなく、「作る」ほうにまわるのです。
いちばん大きなちがい:「失敗しても大丈夫」
そして、いちばん大事なのはここです。
プログラミングでは「失敗してOK」なんです。
まちがってもはずかしくありません。だれでもバグ(こわれたコード)を作ります。バグを見つけて、直すのが、プログラミングの大事な時間なんです。
ある子は、キャラクターが画面いっぱいに広がってしまうバグを見て、「先生、ねこがビルくらい大きくなった!」と笑っていました。でもそのあと、「サイズを1000にしちゃってた」と気づいて、自分でなおしていました。
ほとんどの習いごとでは、「まちがえたらダメ」という雰囲気があります。でもプログラミングはちがいます。
プログラミング教室では、「まちがえても、そこから学べる」ことを自然と体験します。これは、将来どんな仕事をするにしても、ぜったいに必要な力です。
「うちの子が『失敗って楽しいかも』って言ったとき、本気でびっくりしました。」
まずは体験してみませんか?
塾では教えてくれません。ピアノでも学べません。でもプログラミングなら、まちがえることが、前に進む力になります。だからこそ、すべての子どもに一度は体験してほしいと思っています。
お子さまにもプログラミング、合うかもしれません。全教室で無料体験レッスンを実施中です。まずは予約してみてください。
「こわれた!」を「なおせた!」に変える体験が、週に一度の楽しみになるかもしれません。